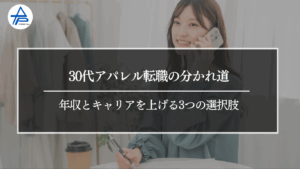「あの人はなぜ店長に選ばれたんだろう?」「自分もいつかは店長になりたいけど、何が足りないんだろう?」
販売員としてキャリアを積む中で、多くの人が一度はこう考えたことがあるのではないでしょうか。
優れた販売スキルを持っているだけでは、必ずしも店長になれるわけではありません。
店舗全体をまとめ、売上と人材の両方を成長させる「店長」というポジションには、販売員とは違う特別な資質が求められます。
この記事では、多くの店長に共通する7つの特徴から、これからの時代に必須となる3つの新スキル、そして店長という目標を達成するための具体的なキャリア戦略までを徹底的に解説します。
記事を読み終える頃には、あなたが目指すべき店長像と、そのために明日から何をすべきかが明確になっているはずです。
目次
「デキる販売員」との違いはここにある!店長に共通する7つの特徴

個人の売上を追求するエース販売員と、店舗全体の成功に責任を持つ店長。両者の間には、スキルセットに明確な違いがあります。
ここでは、多くの優秀な店長に共通して見られる7つの本質的な特徴を解説します。
特徴① 周囲を巻き込む「リーダーシップ」
店長に最も不可欠なのが、チームを一つの方向に導くリーダーシップです。
これは、ただ指示を出すことではありません。
自らが店舗のビジョンや目標に情熱を持って語り、スタッフ一人ひとりの「自分も貢献したい」という意欲を引き出す力です。
目標達成が困難な時でも、決して諦めず、率先して行動する姿を見せることで、チーム全体の士気を高めます。
特徴② 心を動かす「コミュニケーション能力」
店長は、スタッフ、お客様、そして本社や取引先など、多くの人と関わるハブのような存在です。
相手の立場や状況に合わせて伝え方を変え、円滑な人間関係を築く高度なコミュニケーション能力が求められます。
特に、スタッフの些細な変化に気づき、適切な声がけをすることで信頼関係を深め、誰もが意見を言いやすい風通しの良い雰囲気を作り出すことが大事です。
特徴③ 未来を読む「計画性」と「問題解決能力」
日々の売上目標を達成するためには、それを月間、年間といった長期的な視点で捉え、達成までの具体的なアクションプランを立てる計画性が必要です。
また、予期せぬ欠品やスタッフの急な欠勤といったトラブルが発生した際に、冷静に状況を分析し、最善の解決策を迅速に導き出す問題解決能力も、店舗を安定して運営する上で欠かせません。
特徴④ 成長を促す「謙虚さ」と「傾聴力」
優れた店長は、「自分は完璧ではない」ことを知っており、常に学び続ける謙虚な姿勢を持っています。
自分の間違いを素直に認め、スタッフからの意見や提案にも真摯に耳を傾けます。
この傾聴力は、スタッフの自主性を引き出し、チーム全体の成長を促す土壌となります。
部下の成功を自分のことのように喜べる器の大きさも、信頼されるリーダーの共通点です。
特徴⑤ ブランドを体現する「アンバサダーシップ」
店長は、その店舗で最もブランドの世界観を理解し、体現する「歩く広告塔」でなければなりません。
ブランドの歴史や商品に込められた想いへの深い愛情を持ち、それを自身の立ち居振る舞いや接客スタイルで表現します。
その情熱がお客様やスタッフにも伝わり、店舗全体のファンを増やしていくのです。
特徴⑥ 数字で語る「マネジメント能力」
情熱やセンスだけでなく、客観的なデータに基づいて店舗を運営する能力も不可欠です。
売上、客単価、在庫回転率、人件費といった店舗運営に関わる数値を理解し、「なぜ売上が良いのか」「どこに課題があるのか」を論理的に分析します。
そして、その分析結果を基に、具体的な改善策を立てて実行に移す力が求められます。
特徴⑦ スタッフを束ね育てる「育成力」「ピープルマネジメント力」
店長の重要な仕事の一つが、スタッフの育成です。一人ひとりの個性や強みを見抜き、それぞれに合った指導や目標設定を行うことで、個人の成長をサポートします。
また、チーム全体のモチベーションを維持し、スタッフが安心して長く働ける環境を整える「ピープルマネジメント」の視点も、人材が定着し、店舗が継続的に成長していくためには欠かせません。
これからの時代に必須!店長に求められる“3つの新スキル”

従来の店長に求められてきた資質に加え、現代の急速な社会変化に対応するためには、新しいスキルセットが不可欠です。
ここでは、これからの時代の店舗運営を成功に導くために、特に重要となる3つのスキルを解説します。
新スキル① DX時代の「デジタルリテラシー」
現代の店舗運営は、もはやPOSデータの分析だけでは成り立ちません。
デジタルツールを駆使して、オンラインとオフラインを融合させた新しい顧客体験を創造する力が求められています。
具体的には、以下のような能力が不可欠です。
- 顧客管理システム(CRM)の活用: 顧客データを分析し、一人ひとりに合わせたアプローチを行う。
- SNSでの情報発信: InstagramやTikTokなどを活用し、店舗の魅力や新商品を効果的に発信する。
- ライブコマースの企画・実行: オンライン上でリアルタイムに商品を販売し、顧客との新たな接点を創出する。
- ECサイトとの連携: 店舗とECサイトの在庫を一元管理し、販売機会の損失を防ぐ(OMOの推進)。
新スキル② 人材不足を乗り切る「エンゲージメント向上力」
深刻な人材不足が続く中、スタッフに「この店で、この店長のもとで働き続けたい」と思ってもらうことは、店舗運営の生命線です。
給与や待遇だけでなく、一人ひとりのキャリアプランに寄り添い、成長の機会を提供し、仕事へのやりがいや貢献実感といった「エンゲージメント」を高める力が必要になります。
スタッフのエンゲージメントが高い店舗は、離職率が低いだけでなく、顧客満足度も高い傾向にあります。
新スキル③ Z世代を惹きつける「サステナブルへの理解」
特に若い世代のお客様やスタッフにとって、企業やブランドが環境問題や社会問題にどう向き合っているかは、そのブランドを選ぶ上での判断基準になっています。
サステナビリティに関する基本的な知識を持ち、自店舗でできる廃棄ロスの削減やリサイクル活動などをスタッフと共に考え、実行していく姿勢が求められます。
ブランドのサステナブルな取り組みをお客様に自信を持って伝えられることは、Z世代からの共感と信頼を得る上で不可欠です。
▼以下も一緒に読んでみてください。
販売員に資格は必要?未経験からアパレル業界へ転職したい人の疑問に答えます
スタッフの本音|アンケートで分かった「理想の店長」の姿

ここまで店長に求められるスキルを解説してきましたが、実際に現場で働くスタッフは、店長にどのようなことを求めているのでしょうか。
ここでは、多くの販売員の声から見えてきた、「理想の店長」と「残念な店長」の具体的な姿を紹介します。
「ついていきたい」と思われる店長、3つの共通点
スタッフが心から「この人のもとで頑張りたい」と感じる店長には、共通する3つのポイントがあります。
①一人ひとりを「個人」として見てくれる
売上などの数字だけでなく、スタッフそれぞれの個性や得意なこと、悩んでいることにきちんと目を配り、気にかけてくれる店長です。
「最近、〇〇さんの接客、すごく良くなったね」「疲れてない?」といった日々の小さな声がけが、スタッフの「自分のことを見てくれている」という安心感とモチベーションに繋がります。
②人によって態度を変えず、公平である
ベテランと新人、売上が良いスタッフとそうでないスタッフなど、相手によって態度を変えることなく、誰に対しても公平に接することができる店長です。
特に、ミスが起きた際には、感情的に個人を責めるのではなく、チーム全体の問題として捉え、冷静に解決策を示してくれる姿勢が、スタッフからの厚い信頼を得ます。
③人として尊敬できる
仕事のスキルはもちろんのこと、いつも前向きで一生懸命だったり、スタッフの成功を心から喜んでくれたり、困ったときには全力で守ってくれたりする姿勢です。
こうした人間的な魅力が、「この店長みたいになりたい」「この店長を支えたい」という、チームの強い一体感を生み出します。
これはNG!「残念な店長」と思われる人の言動
一方で、スタッフのやる気を削いでしまう「残念な店長」にも、いくつかの共通した言動が見られます。
| 残念な言動 | スタッフへの影響 |
| 言うことがコロコロ変わる | 指示に一貫性がなく、スタッフは何を信じて動けばいいのか分からず混乱してしまう。 |
| 感情の起伏が激しい | スタッフは常に店長の顔色をうかがうようになり、店舗全体が委縮し、意見が言えなくなる。 |
| 自分の成功体験ばかり話す | 「昔はこうだった」という話が多く、スタッフの自主性や新しい挑戦の芽を摘んでしまう。 |
| 特定の人だけをえこひいきする | チーム内に不公平感が生まれ、全体のモチベーションが低下する原因になる。 |
| 責任をスタッフになすりつける | トラブルが起きた際にスタッフを守らず、責任転嫁するため、信頼関係が根本から崩れてしまう。 |
あなたの店長はどのタイプ?4つのリーダーシップスタイル診断

リーダーシップの形は一つではありません。店長がどのようなスタイルでチームをまとめているかによって、店舗の雰囲気やスタッフの育ち方は大きく変わります。
ここでは、代表的な4つのリーダーシップスタイルを紹介します。
ご自身やあなたの上司がどのタイプに近いかを知ることで、自己分析や、今後のチームとの関わり方のヒントが見つかるかもしれません。
① 細かく指示して導く「コーチ型」
<こんな店長>
「まずはこうやってみて」「次はこれをお願い」というように、仕事の進め方を具体的に、細かく指示してくれます。
新人スタッフや経験が浅いチームをまとめるのが得意です。
- 長所: スタッフは迷うことなく、安心して業務を進めることができます。店舗全体の業務レベルを均一化しやすいのが強みです。
- 注意点: 指示が細かすぎると、スタッフが自分で考える機会を奪ってしまい、自主性が育ちにくくなることがあります。
② スタッフを支え、環境を整える「サポーター型」
<こんな店長>
「何か困っていることはない?」「どうすればもっと働きやすくなるかな?」と、スタッフ一人ひとりの声に耳を傾け、働きやすい環境を作ることを最優先に考えます。
縁の下の力持ちタイプです。
- 長所: スタッフは安心して長く働くことができ、チームの一員であるという意識が強まります。店舗の一体感を高めるのが得意です。
- 注意点: スタッフの意見を尊重するあまり、ときには厳しい決断や指示ができなくなってしまうことがあります。
③ 情熱とビジョンで引っ張る「牽引型」
<こんな店長>
「この店を地域で一番にしよう!」「私たちの接客でお客様を感動させよう!」といった熱い想いや大きな目標を掲げ、その背中でチームを引っ張っていくタイプです。
カリスマ性があります。
- 長所: チーム全体の目標が明確になり、高いモチベーションを生み出します。困難な状況でも、チームを鼓舞して前に進める力があります。
- 注意点: 店長の想いが強すぎると、スタッフがついていけなくなったり、意見を言いにくくなったりすることがあります。
④ スタッフを信じて任せる「委任型」
<こんな店長>
「このディスプレイは〇〇さんにお願いするね」「この件は〇〇さんの判断に任せるよ」と、スタッフを信頼して大きな裁量を与えます。
ベテランスタッフが多いチームで力を発揮します。
- 長所:任されたスタッフは責任感とやりがいを感じ、大きく成長することができます。店長自身も、より重要な業務に集中できます。
- 注意点: スタッフのスキルや経験を見誤ると、「丸投げ」や「放任」と受け取られ、チームが混乱する原因になります。
どのスタイルが一番良いというわけではありません。
大切なのは、お店の状況やスタッフの成長度合いに合わせて、これらのスタイルを柔軟に使い分けることです。
店長に向いていない人の特徴

「店長になりたい」という気持ちとは裏腹に、どうしても店長の役割に必要な資質と自分の特性が合わない、という場合もあります。
ここでは、店長という役割を担う上で、ハードルとなる特徴を解説します。
ご自身のキャリアを考える上での自己チェックとして、また、現在の上司への理解を深めるための客観的な視点として、参考にしてみてください。
① チームより「個人プレー」が好き
チームで目標を達成することよりも、自身の販売スキルを磨き、個人の売上目標を追いかけることに大きな喜びを感じる人は、プレイヤーとしての資質が高いと言えます。
店長の役割は、自分が売ることではなく「チームに売らせること」にシフトします。
自分の成功よりもチームの成功を喜べない場合、スタッフの育成やチームビルディングといった店長の大切な仕事に、やりがいを見出すのが難しいでしょう。
② 人に興味が持てない・向き合うのが苦手
店長は、スタッフ一人ひとりの個性や価値観、悩みに関心を持ち、ときにはプライベートな相談に乗ることも求められる仕事です。
もし、他人の感情の機微を察したり、根気強く話を聞いたりすることにストレスを感じるなら、スタッフからの信頼を得てチームをまとめるのは困難かもしれません。
③ 責任を負うのが怖いと感じる
店舗で発生するすべての問題の最終的な責任は店長にあります。
売上不振やクレーム、スタッフ間のトラブルなど、厳しい状況でも矢面に立ち、決断を下さなければなりません。
プレッシャーのかかる場面で責任ある立場に立つことを避けたいと感じる場合、店長の重圧は大きな負担になるでしょう。
④ 変化よりも安定を求める
店舗運営では、本社の戦略変更、新しいシステムの導入、客層の変化など、常にさまざまな変化への対応が求められます。
これまで慣れ親しんだやり方を変えることに抵抗を感じたり、新しいことを学ぶのが億劫だと感じたりする場合
変化のスピードが速い現代の店舗運営に適応していくのは難しいかもしれません。
⑤ 数字やデータを見るのが苦痛
接客のセンスや感覚には自信があるものの、売上データや在庫の数字など、細かいデータを見て分析したり、それに基づいて計画を立てたりするのが苦手な人もいます。
しかし、現代の店舗運営は、客観的なデータに基づいた論理的な判断が不可欠です。
数字を根拠に店舗の課題を見つけ、改善策を実行する能力がなければ、継続的に売上を伸ばしていくことは難しいでしょう。
もちろん、これらの特徴に当てはまるからといって、絶対に店長になれないわけではありません。
これらは、店長を目指す上での「伸びしろ」と捉えることができます。
自分の得意・不得意を客観的に理解することが、キャリアプランを考える上での第一歩です。
▼以下も一緒に読んでみてください。
アパレル店員に向いている人の特徴8選|向き不向きにあったキャリアも紹介
店長になるには?目標達成のための具体的なキャリア戦略

店長になるという目標を達成するためには、日々の業務の中で戦略的に行動し、自身の価値をアピールしていく必要があります。
ここでは、「現職で昇進を目指す場合」と「転職してポジションを掴む場合」の2つの道筋に分けて、具体的なアクションプランを解説します。
【現職編】上司に「店長候補」として意識させるためのアピール術
現在の職場で店長を目指すなら、まずは上司や会社から「次の店長候補はこの人だ」と認識してもらうことが最も大切です。
①常に「店長視点」で考え、発言する
いち販売員としての視点だけでなく、「もし自分が店長だったらどうするか?」という視点で常に物事を考えましょう。
店舗の売上や課題について自分なりの分析や改善案を持ち、ミーティングなどの場で「売上をさらに伸ばすために、〇〇を試してみてはいかがでしょうか」と具体的に提案する姿勢が、上司の目に留まるきっかけになります。
②率先して「損な役回り」を引き受ける
新人教育や在庫管理、クレーム対応の一次窓口など、他のスタッフが少し面倒だと感じるような役割を積極的に引き受けましょう。
これらの業務は、店舗運営の裏側を理解し、マネジメントの基礎を学ぶ絶好の機会です。
チームへの貢献意欲の高さが評価され、信頼に繋がります。
③自分の言葉で「店長になりたい」と伝える
日々の行動で示すだけでなく、上司との面談などの機会に、はっきりと「将来は店長としてこのお店に貢献したい」というキャリアプランを伝えましょう。
明確な目標を持っていることを示すことで、会社もあなたを「投資すべき人材」と認識し、研修の機会などを与えてくれる可能性が高まります。
【転職編】店長ポジションを勝ち取るための2つの道
現在の職場での昇進が難しい場合や、より良い条件を求めるなら、転職も有効な選択肢です。
①サブ(副店長)経験を積み、次の転職で店長へ
未経験からいきなり店長として転職するのは簡単ではありません。
まずは店長候補やサブ(副店長)のポジションで求人を探し、そこでマネジメント経験を1〜2年積むのが着実なステップです。
一度マネジメント経験を積めば、次の転職で店長のポジションを狙える可能性は格段に上がります。
②新規オープン店舗の店長を狙う
新しくオープンする店舗では、既存の店舗と異なり、オープニングスタッフとして店長を外部から募集することがよくあります。
これは、ブランドや企業が新しい風を求めているケースが多く、ポテンシャルを重視した採用が行われやすいからです。
求人サイトで「新規オープン」「オープニングスタッフ」といったキーワードで検索してみることをお勧めします。
面接で「この人なら任せられる」と思わせる自己PRの作り方
店長の面接では、「個人として売れる」ことよりも、「チームを率いて店舗を成功させられる」ことを証明する必要があります。
自己PRでは、以下の3つの要素を必ず盛り込みましょう。
リーダーシップを発揮した具体的なエピソード
「後輩の指導で、〇〇という課題に対し、△△という方法でアプローチした結果、後輩の売上が前月比120%になった」など
具体的な状況・課題・行動・結果をセットで語れるように準備しましょう。
数字に基づいた実績
「個人売上〇ヶ月連続達成」といった個人の実績に加え、「私が担当した□□のキャンペーンでは、チームで目標比150%の売上を達成しました」など、チームを巻き込んで成果を出した実績を数字で示すことが大切です。
店長として実現したいビジョン
最後に、「貴社の〇〇という理念に共感していて、私が店長になった際には、△△という強みを活かして、▢▢のようなお客様に愛される店舗を作りたい」というように、自分のビジョンと企業の方向性を結びつけて語ることで、熱意と貢献意欲を強くアピールできます。
▼以下も一緒に読んでみてください。
販売員から転職|異業種でも成功する人の共通点とキャリアチェンジ戦略
【まとめ】店長は「才能」ではない。キャリアの次なるステージへ

この記事では、多くの優れた店長に共通する特徴から、これからの時代に求められる新しいスキル、そして店長になるための具体的なキャリア戦略までを解説してきました。
店長とはただ「販売スキルが高い人」がなれるポジションではありません。
チームをまとめ、スタッフを育て、店舗全体の売上と成功に責任を持つ、まったく別の役割です。
求められる資質はさまざまですが、それらは決して生まれ持った「才能」だけで決まるものではありません。
本記事で紹介したリーダーシップやマネジメント能力、そして新しい3つのスキルは、すべて日々の業務の中で意識し、行動を積み重ねることで、後から着実に身につけていくことができるものです。
大切なのは、まず自分に足りないものを客観的に認識し、その上で「理想の店長像」に向かって、明日から具体的に何をするかを計画し、実行に移すことです。
この記事が、あなたがキャリアの次なるステージへ踏み出すための、具体的な道しるべとなれば幸いです。
もし、ご自身の強みを活かしたキャリアプランについて、あるいは店長を目指す上での具体的な戦略についてプロの意見を聞いてみたいという方は
ぜひ一度私たちアプライムにご相談ください。あなたの挑戦を、専門的な知見をもって全力でサポートします。